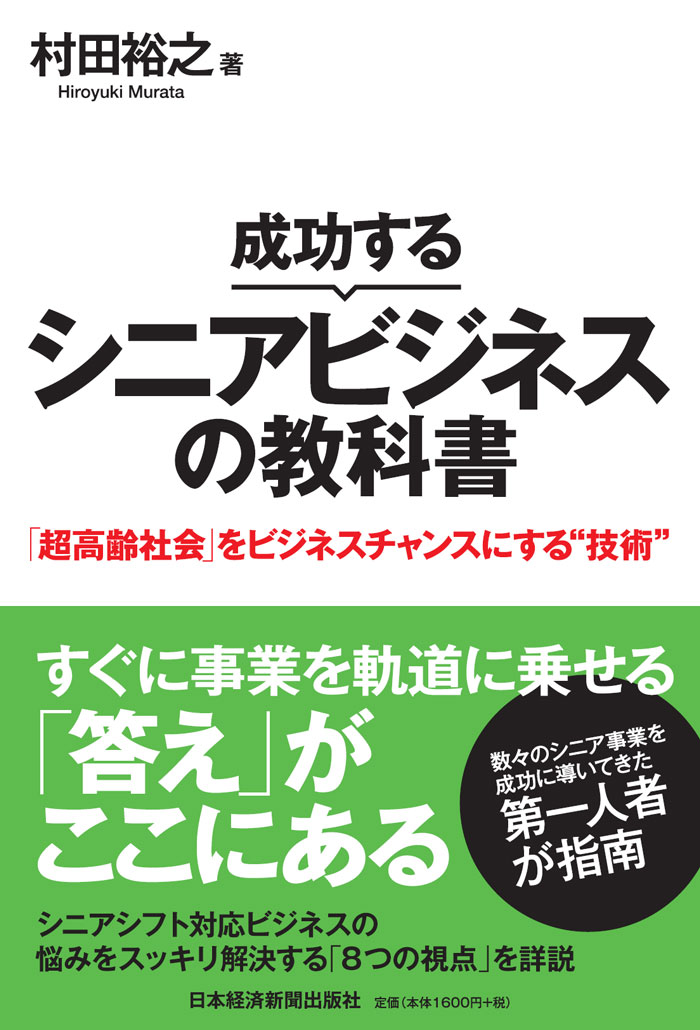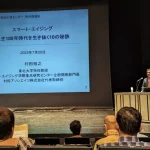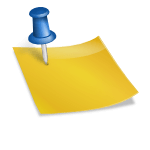2024年5月22日 中国一億中流集団訪日団
増えている中国企業経営者による研修・視察団
都内の会場で中国企業の経営者グループ向けに講演を行いました。
今回来日したメンバーは、企業経営者約50人で、年齢層は60代から20代まで幅広く、女性経営者も半分程度。業界は多岐に渡っており、介護も含めたシニアビジネスを検討している人たちとのことでした。
講演テーマは、先方からのリクエストで「高齢社会におけるビジネスチャンス発見の秘訣」。内容は、拙著「成功するシニアビジネスの教科書」の抜粋です。
Amazonマーケティング・セールスなど2部門で1位!シニアシフト対応ビジネスの悩みをスッキリ解決する「8つの視点」を詳説。数々のシニア事業を成功に導いてきた筆者が、ビジネス成功の秘訣をまとめたシニアシフト対応ビジネス指南書の決定版。世界各国から注目を浴びる日本のシニアビジネスを常にリードする先駆者が15年間の体験の知恵を遂に開示。全てのビジネスパーソン必読書。韓国・台湾でも出版されたシニアビジネスのバイブル!
昨年11月に中国からの別の企業グループに講演した時には、質問の大半が日本の年金制度と日本のシニアの月の支出額と費目に関するものでした。
ところが、今回は前回の質問は全く尋ねられず、「意外な」質問を尋ねられたのが興味深かったです。
質問1:シニアは資産が多いなら、資産運用すれば良いと思うがどうか?
拙著に「シニア市場の正しい見方」の一つとして「シニア層は、他の年齢層より資産は多いが、所得は少ない」という説明があり、世帯主の年齢階級別 正味金融資産と年間所得のグラフを説明したことへの質問でした。
私はこれまでこの話を何百回としていますが、日本人からこういう質問をされたことはありませんでした。質問者は40代くらいの男性でしたが、資産があるなら投資をするのが当たり前では?という雰囲気でした。
日本のシニアの多くは、一般に将来に対する明るい展望が見られないと思いがちな。このために、3K不安(健康不安、経済不安、孤独不安)が強く、いざ高額出費が必要という時のために備えてお金を蓄える傾向が強いのです。
資産があるといっても、将来不安に対する備えであり、できるだけ手をつけたくない。かつ、目減りさせたくない、という気持ちが強く、リスクのある投資への意欲は必ずしも強くありませんでした。
もちろん、シニア一人ひとりの消費行動は多様なので、こうした消費スタイルが全ての人にあてはまるわけではありません。
質問2:シニア向け商品やサービスをひとまとめにした店舗はどうか?
質問者の意図は、シニア層が必要とする商品・サービスがひとまとめにあれば、利便性が上がり、集客力が上がるのではないか、ということでした。
結論から言うと、日本ではこうした店舗・モールで成功した事例があまりありません。
かつて、大手スーパーのイオンがシニアシフト戦略を推進していた頃、西葛西にあるイオン葛西店をそうした店舗にしようとしましたが、かなり苦戦しました。
新宿の京王百貨店や上野の松坂屋は一時期、シニア向け対応に注力し、速度が極端に遅いエスカレーターを導入したり、休憩用の椅子をあちこちに置いたりしましたが、今はなくなりました。
「おばあちゃんの原宿」と言われて久しい巣鴨の商店街は、ここ20年進化しておらず、活気がなく、一度行けば十分と言う感じです。
一言で言うと、「シニア向け」を前面に打ち出した店舗やモールは、辛気臭くなるのです。結果、シニア自身が行きたいと思うような場所にならないのです。
質問3:日本では子供に財産を残す人と残さない人の割合はどうか?
これも一概に言えませんが、日本では団塊世代を境に、若い世代は子供に財産を残すより自分のために使うという人の割合が確実に増えています。
質問者は30代くらいの男性でした。こうした質問が出てくるのは、中国でも都市部の人たちのメンタリティーは、かなり日本の都市部の人に近いことを示しています。
他にも数多くの質問が出ましたが、割愛します。
中国も特に都市部の一人当たりのGDPが急上昇していること、少子化・高齢化のペースが上がっていることから、介護以外のシニア市場が広がっていく時期もそう遠くないことを感じました。