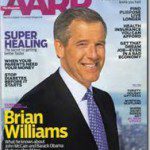スマートシニア・ビジネスレビュー 2003年1月15日 Vol. 24
 出版不況といわれる中で、昨年120万部売れた「生き方上手」の著者 日野原重明さんが、90歳を越えた今も現役の医師として活躍されていることはよく知られています。
出版不況といわれる中で、昨年120万部売れた「生き方上手」の著者 日野原重明さんが、90歳を越えた今も現役の医師として活躍されていることはよく知られています。
しかし、上には上がいるもの。約11年前の1992年3月に百歳のピアニストを記念するコンサートがアメリカで企画されました。
ただし、これは百歳の記念に親戚・友人が集まって演奏会を開くのではありません。百歳でなお現役のプロのピアニストが、音楽の殿堂カーネギー・ホールで、譜面なしに2時間ピアノを弾きとおすというものでした。
そのピアニストの名は、ミエチスラフ・ホルショフスキー。ポーランドのリヴォフ(現ウクライナ)生まれのこの人は、戦前ソリストとして活躍し、チェロの神様パブロ・カザルスとの邂逅を得た後、カザルスの良き共演者としてその名を馳せた知る人ぞ知る伝説の大ピアニストです。
日本に比べ、欧米のピアニストには長命の人が多いようです。ベートーヴェン弾きで有名なバックハウスは85歳で亡くなる1週間前まで演奏会に出ていました。また、ショパン弾きで有名なルービンシュタインも88歳まで現役でした。しかし、百歳で現役のピアニストだったのは、このホルショフスキーだけです。
ルービンシュタインが引退したのは、晩年に視覚障害が進んだためです。実は、ホルショフスキーもルービンシュタインと同じ視覚障害になりました。しかし、ルービンシュタインとの違いは、「目なんか見えなくたって、ピアノくらい弾けるよ」といって、視力が無くなっても引退しなかったことです。
この大ピアニストが1987年についに来日しました。お茶の水のカザルス・ホールのこけら落としに招かれたためです。この時、すでに95歳。伝説のピアニストの演奏を聴くために5百人を超える人が集まりました。その時の様子が石井宏著「帝王からマフィアまで」に詳しく書かれています。
「プログラムの前半が終わったとき、休憩時間のロビーでは、人はみな異常な感動に包まれており、いま目の前で起きたことが信じられないといった顔をしていた。ピアノがあのような音を立て、あのような世界を作り出すということが信じられないのである。」
日本のモーツアルト演奏の第一人者とされる小林道夫さんは次の言葉を残しています。
「あれを聴いていると、人間50歳なんてまだ洟垂れ小僧のような気がしました。あのピアノが、道夫や、いいかい、モーツアルトはこうやって弾くんだよ、と語っているような気がしました」
また、1990年4月に98歳になったホルショフスキーの演奏会を、やはりカーネギー・ホールで実際に聴いた石井氏は、その演奏について次のように語っています。
「カーネギー・ホールのコンサートでも、いささかも"老い"を感じさせたり、指や気力の衰えを感じさせたことはなく、その演奏は若者より精気に溢れていた。それは人間の可能性というものを極限まで広げて見せてくれた」
98歳になっても単に「ピアノが弾ける」というのではなく、演奏技術、パワー、音楽性の全てにおいて、現役ピアニストのトップクラスであったことが何よりも驚きです。
一方、これと対照的な記事が日経ビジネスの最新号に載っていました。小学校の教員の平均年齢が40代後半になっており、急速な"高齢化"が進んでいるとのこと。大都市圏の小学校には50代の教員がごろごろしており、小学生たちは「老人ホーム」に通っているようなものだ、というのです。
老人ホームというのはいささか極端なたとえですが、50代と言う年齢の位置づけが見方によってこれほどまでに異なるものかという気がします。私は、この記事を見て大学3年の時に、退官される教授が挨拶で語った次の言葉を思い出しました。
「私は、これから人生の下り坂を降りていきますが、皆さんはこれからが上り坂です」
ある人にとって、50代は洟垂れ小僧なのに対し、別の人にとって、50代は人生の下り坂となる。この差は、一体どこから来るのでしょうか。
まず、自分の未熟さを素直に認めることができること。そして、人間の可能性をどこまでも信じ、より高きものを目指して、謙虚に自分を磨き続けられるかで差がでるのだと私は思います。
ホルショフスキーの盟友カザルスが、自由自在にチェロを弾くのをやっかむ人たちに対して、こう言いました。
「人々は私が、鳥が歌うのと同じように楽々と演奏するといいます。鳥たちが自分の歌をうたうために、どんなに大きな努力を重ねているのか、知らないからでしょう」
そのカザルスが晩年、好んで弾いた曲が母国カタロニアの民謡「鳥の歌」でした。1971年に国連でこの曲を演奏したときに、カザルスが次の挨拶をしたことは今も語り草になっています。
「カタロニアの小鳥たちは、青い空に飛び上がるとピース、ピースといって鳴くのです」
ピアノ伴奏は、もちろん、ホルショフスキーでした。