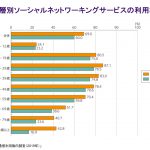2012年4月10日号 シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第61回
エイジフレンドリーとは本来、高齢者にだけ親和性が高いわけではない
エイジフレンドリー(age-friendly)とは本来「ある特定の年齢層に親和性が高い」という意味だ。したがって「特定の年齢層」を高齢者層に限っているわけではない。
1960年代から70年代の高度成長期に全国各地に多摩ニュータウン、高島平団地、千里ニュータウンなど多数の住宅団地が建設された。これらの団地は主に当時20代だった団塊世代の人たちの住宅需要に応えるために建設されたものだ。
当時最も重要視されたのは、夫婦プラス子供数人のファミリー層で取得可能な価格だった。このため、間取りは、いわゆる「団地サイズ」の部屋で構成される2LDKが一般的だった。現代の集合住宅と比べればかなり狭いが、当時は「それが当たり前」の標準とみなされた。その時代の20代のファミリー層に対しては親和性が高く、この意味においてエイジフレンドリーだった。
しかし、入居後40年、50年と経過し、団地の仕様が高齢化した入居者のニーズと合わなくなっている。三階以上の建物でもエレベーターがないところでは、下半身の衰えた年配者には昇降が辛い。部屋には多くの段差があり、間口が狭く、至るところにバリアがある。
このように、時間軸のある時点で特定の年齢層に親和性が高くても、時間の経過とともに親和性が低くなる。この理由は、コミュニティの構成員である団地の入居者がエイジングにより身体機能など多くの面で変化するとともに、コミュニティの建物・インフラもエイジングにより経年劣化するからである。
多摩ニュータウンのような大規模な住宅団地は、日本以外の新興国でも多く見られる。たとえば、シンガポールでは国民の8割がHDBという公営の高層住宅に住んでいる。
香港では狭い土地に高層・超高層住宅が林立しており、日本よりも住宅同士の間隔が狭く、密集している。これらの国では、高齢化率がまだ11%程度だが、日本以上に少子化が進んでいるため、20年後には現在の日本並みになると予測されている。だから、20年後にこれらの国の住宅団地で何が問題になるのかが容易に予想できる。
エイジフレンドリー=シニアフレンドリーの意味合いが強い
近年日本以外のいくつかの地域で「エイジフレンドリーなコミュニティ」という言葉が聞かれる。前号で説明の通り、エイジフレンドリーという言葉は、西洋発のもので、多くの場合、シニアフレンドリー(高齢者に親和性が高い)の意味合いが強い。これは、「時間軸のある時点で特定の年齢層=シニア層に親和性が高い」ことを意味する。
しかし、この概念の欠点は、上述の住宅団地の高齢化に見られるように「時間の経過による変化(経年変化)を考慮していない」ことだ。これが現状のエイジフレンドリーのもう一つの落とし穴である。
このため、Age-friendly(エイジフレンドリー)ではなく、個人、建物・インフラ、コミュニティの経年変化(エイジング)に適応可能なAgeing-friendly(エイジングフレンドリー)こそが、超高齢社会に必要な概念であると筆者は考えている。
この概念に近い例として千葉県佐倉市にある「ユーカリが丘」が挙げられる。ユーカリが丘は1971年から開発が始まり、40年以上経過しているが、他の大規模ニュータウンと異なり、現在も居住人口が増え続けている。
最大の違いはコミュニティにおける人口構成である。他の大規模ニュータウンでは団塊の世代を含む60代以上が全体の60~70%に達しているのに対し、ユーカリが丘では25%程度となっている。しかも、どの年齢層も同じ割合になっている。これは開発を特定時期に集中せず、時間軸で分散させて行ってきたことによる。
他にも一人暮らしになって一軒家を持て余している人にわずか150万円程度でマンションに移り住み可能な仕組み、子育て世代の負担軽減のために鉄道駅そばへの保育所の設置、買い物困難な高齢者向けの団地内周回バスなど、様々な工夫を施している。
ユーカリが丘は、特定の世代だけでなく、全ての世代に親和性が高く、安心して住み続けられるコミュニティを目指している。超高齢社会における街づくりを示唆している先駆例といえよう。