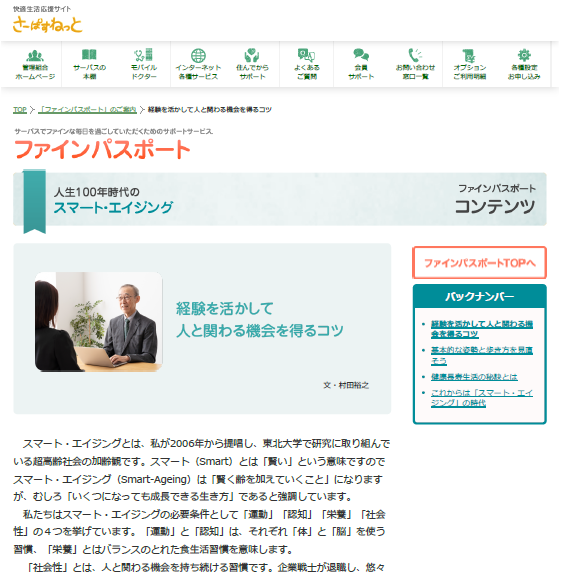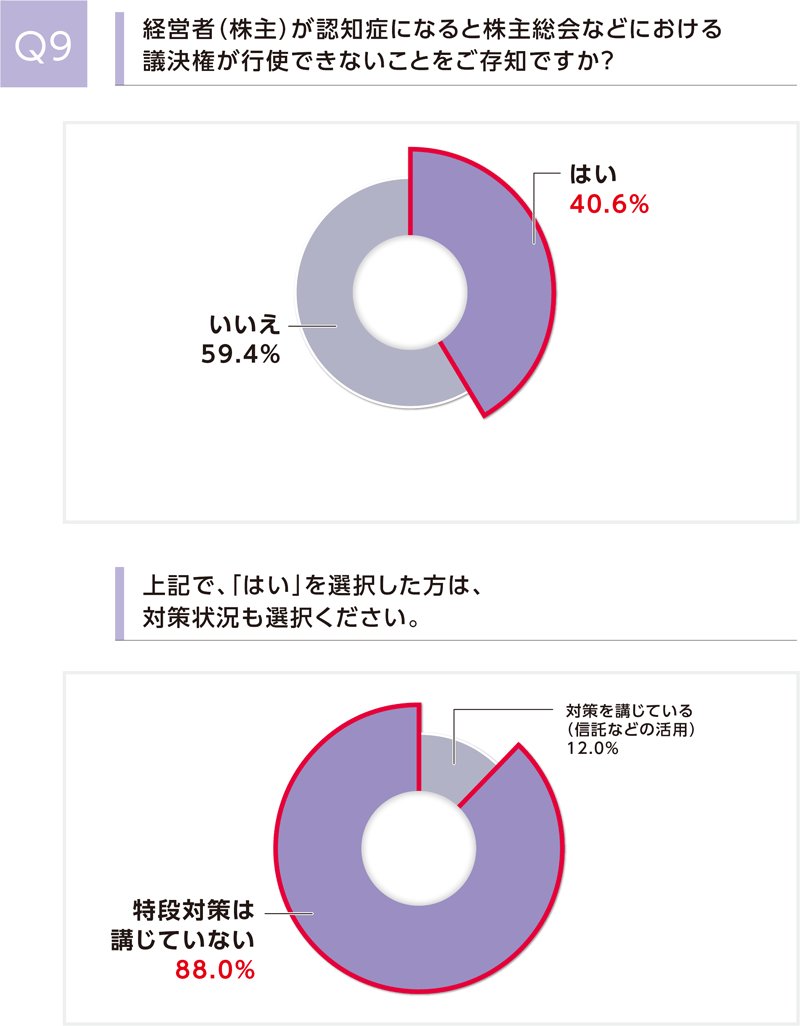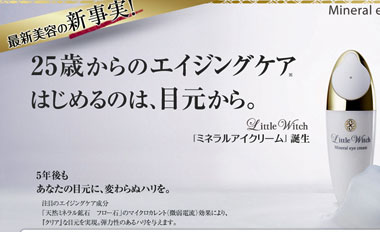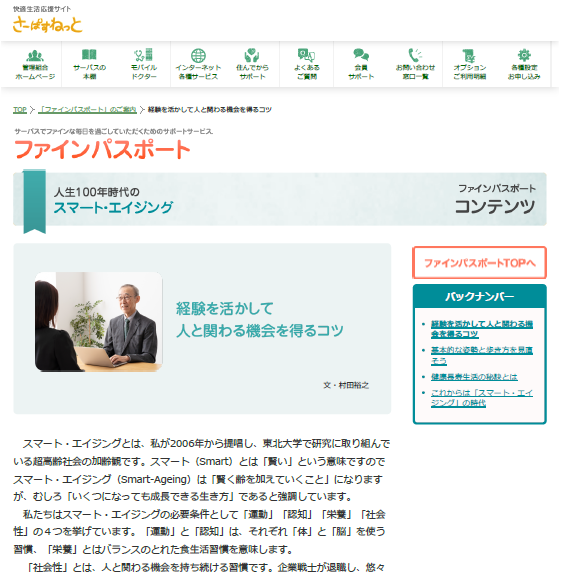
経験を活かして人と関わる機会を得るコツ
- 公開日:
スマート・エイジングの必要条件は「運動」「認知」「栄養」「社会性」の4つ。「社会性」とは、人と関わる機会を持ち続ける習慣。とはいえ、高齢になってから、いきなり地域社会へ飛び込むのは容易ではありません。これまでの経験を活かして「人と関わる機会」を得るための心得を3つお話ししました。
村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ
団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。