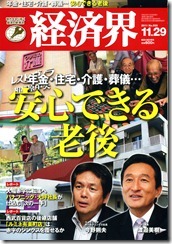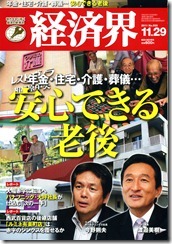今年の正月は「家族会議」で近未来の親の課題を共有しよう
- 更新日:
- 公開日:
不動産経済 連載 あなたの生き方を変えてしまう「親のこと」、知っていますか?第五回 家族会議のすすめ 相続や介護に関わるトラブルは、その背後にある「人間関係のトラブル」であることがしばしば原因となっている。こうしたトラブ […]
村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ
団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。