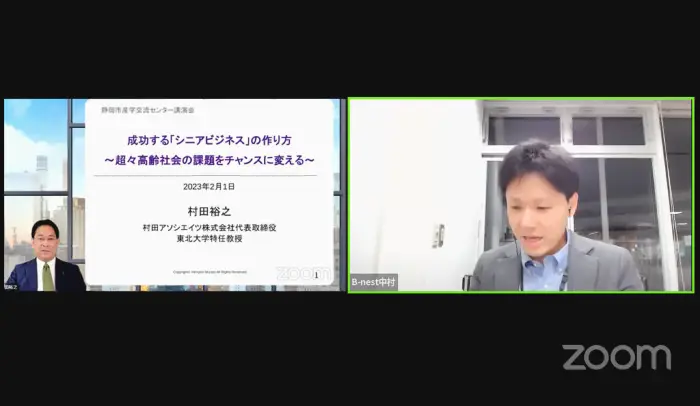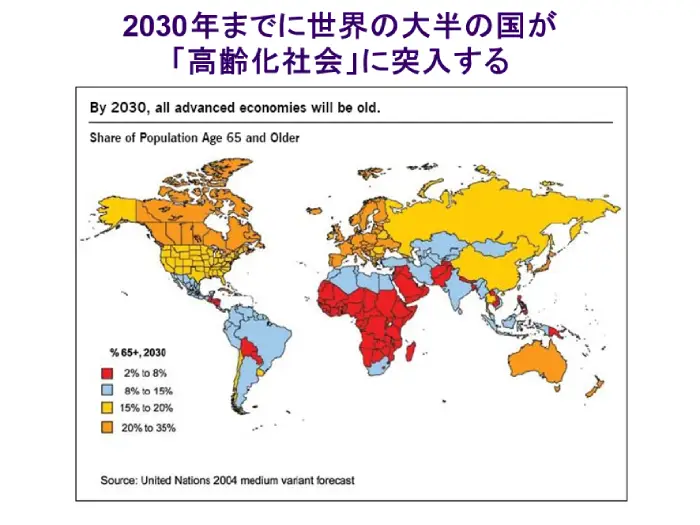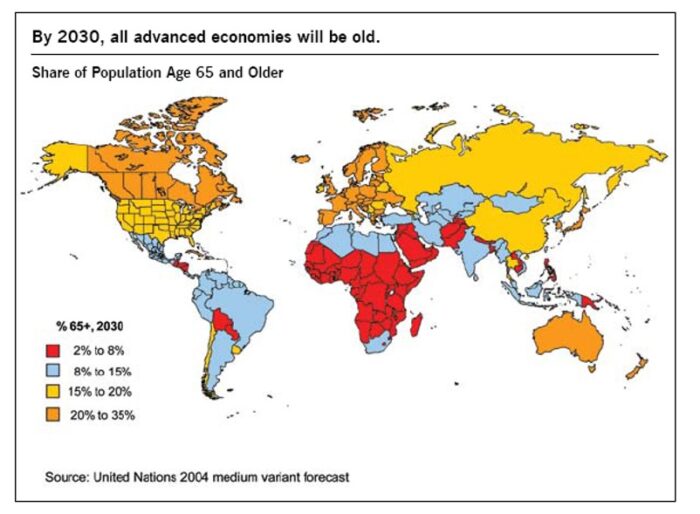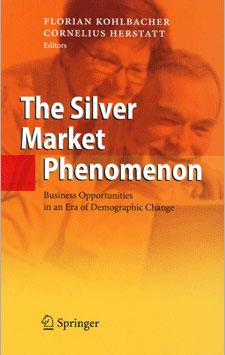フランス政府が推進する「シルバーエコノミー」の動向
福祉の分野で欧州は先進国のイメージが強く、日本の福祉関係者はいまだに欧州詣でをするが、アクティブシニア向けビジネスに関しては、欧州よりも日本の方が進んでいる
村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ
団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。