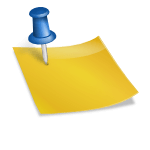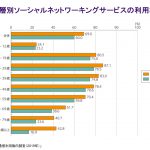1月10日 シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第58回
 中高年を対象に商品・サービスを提示する場合、特定の年齢訴求が受け入れられる場合とそうでない場合がある。最近の例では、サントリーの化粧品F.A.G.E.が該当する。「まだ50代。ハリさえあれば」「60代、弾むハリ」などと新聞広告やチラシでターゲットユーザーの年齢を訴求し、効能を訴えている。
中高年を対象に商品・サービスを提示する場合、特定の年齢訴求が受け入れられる場合とそうでない場合がある。最近の例では、サントリーの化粧品F.A.G.E.が該当する。「まだ50代。ハリさえあれば」「60代、弾むハリ」などと新聞広告やチラシでターゲットユーザーの年齢を訴求し、効能を訴えている。
経済的メリットを感じられる場合はうまくいく
こうした特定の年齢訴求アプローチが受け入れられるのは、明らかに経済的メリットがあると感じられる場合だ。
たとえば、映画や劇場、散髪などのシニア割引が該当する。JR東日本の「大人の休日」は、特定の年齢に達した人向けの鉄道運賃の割引という古典的な例だ。
割引以外の例では、かつてアリコ(現:メットライフアリコ)が発売した「はいれます」という保険商品がそうだった。
一般に年齢が上がると死亡保険は加入しにくくなる。当時、これが発売されるまで、50歳以上の人が医師の審査なしで加入できる死亡保険はほとんどなかった。需要があるのに供給がなかったニッチ市場で大ヒットした商品だ。現在では、同社以外の多くの保険会社が50歳以上でも加入できることを謳うことが一般的となった。
これらのように該当者にとって経済的メリットが感じられる場合、特定の年齢を訴求されても受け入れられる。
差別的ニュアンスが感じられる場合はダメ
一方、ダメな場合は、「差別的ニュアンス」が感じられる場合である。たとえば、後期高齢者医療制度がその典型だ。75歳以上に特化し、保険料負担を増したことで、猛反発を受けた。負担を増したとはいえ、実は現役世代の負担率3割よりも負担割合は少なかった。だが、特定の年齢層の負担増というアプローチは、特定の年齢層への「差別」と見られやすいのだ。
私が以前、アメリカ・パロアルトのシニアセンターを訪れた時、当時の副社長が次のように語っていたのを思い出す。「一般にシニア(Senior)と呼ばれると、年寄り扱いされているようで、嫌な感じがします。でも、シニア割引が提示される時にはシニアと呼ばれてもいいのです」多分にご都合主義ではあるが、これが高齢者の本音だろう。
さて、冒頭の化粧品に話を戻すと、これまでのところ、化粧品は特定の年齢訴求がうまくいかなかった例だ。
かつて、大手化粧品メーカーが50代以上の女性に訴求して大キャンペーンを行ったとき、画期的な試みだとして、多くのメディアに取り上げられた。ところが、肝心の売り上げはさっぱりだった。特定の年齢訴求が、対象者にとっては、特定の「ラベル」を張られるかのように思われたからだ。
このように特定の「ラベル」を張ることをラベリング(labeling)という。ラベリングとは、元来、特殊な事実をもとにしてある人物やある物事の評価を類型的かつ固定的に定めることを意味する。
調査会社などは、よく「認知年齢は実年齢より10歳若い」と言う。だから、60代の人をターゲットにする場合は、50代向けのキャッチコピーを使えと言う。
だが、これは間違っている。認知年齢は実年齢より10歳若いと言うのは、本人が実年齢より10歳若いと認知しているのでない。若い頃に比べ、体力も落ち、肉体的にも衰えてきていることは感じており、自分では十分認知しているものの、そのことを誰かに敢えて指摘されたくない、という複雑な心境を表しているのだ。
ラベリングによる過去の失敗事例に学べ
サントリーの事例では、ラベリングによる過去の失敗事例をよく研究していると思われ、キャッチコピーなどの言葉遣いにいろいろな面で細やかな工夫を施しているのを感じる。顧客から実際にどの程度反応が得られているのか興味深い。
一方、大丸松坂屋百貨店が60歳代の女性をターゲットにした「マダムセレクション」という売り場を始めた。20~30歳代に訴求した売り場がうまくいったために60歳代に対しても取り組むことになったとのこと。すでに松坂屋上野店、大丸京都店に続き、大都市の基幹店に導入するという。
だが、売り場での年齢訴求でも、60歳代に対しては苦戦してきた経緯がある。こうした過去に学んで周到に取り組み、前例を覆してほしいと思う。
*シルバー産業新聞社のご好意により全文を掲載しています。