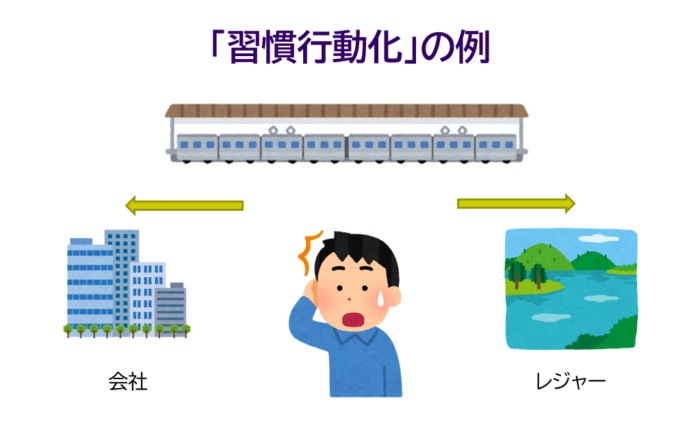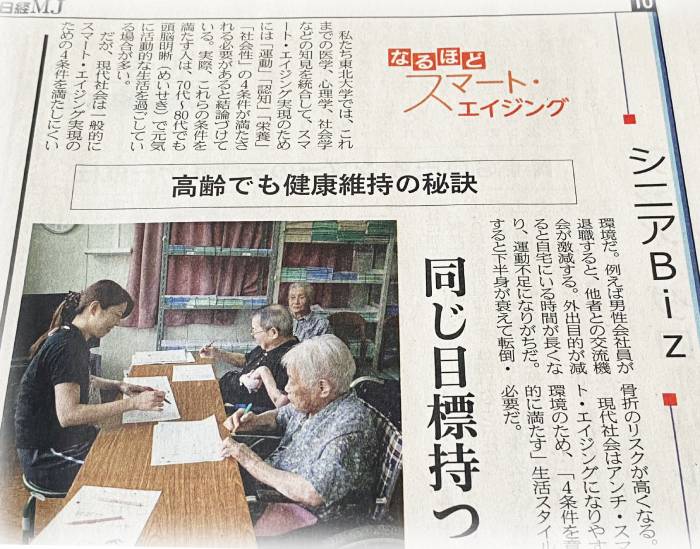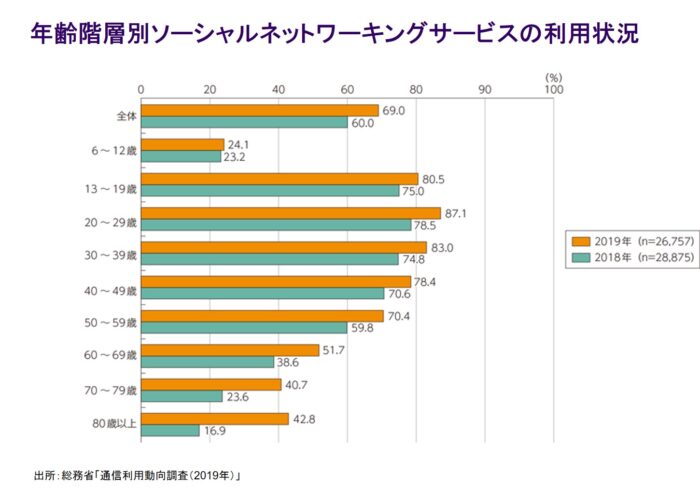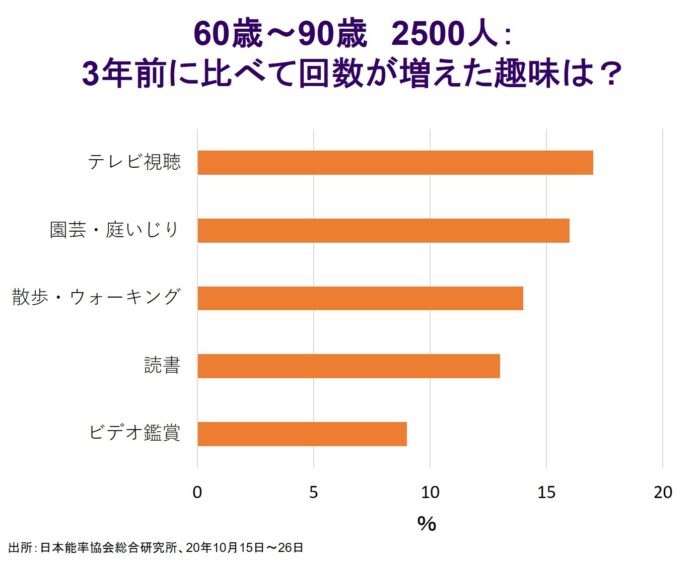1日30分でコロナ太りを解消!男性版カーブス
- 更新日:
- 公開日:
メンズ・カーブスとは、女性専用フィットネスで業界トップのカーブスの男性版です。実は世界中で日本にしか存在しません。理由は日本で商品化されたからです。特長は①筋トレ・有酸素運動・ストレッチの全てが30分で完結する、②個別指導の「セミパーソナル・サービス」を追加料金なしで受けられる、③自分のペースで無理なくできてコスパもよいことです。女性用カーブスではコーチは全員女性ですが、メンズ・カーブスでは男性と女性がコーチとしてサポートします。コーチとのコミュニケーションが多いことで継続の動機が上がることもポイントです。