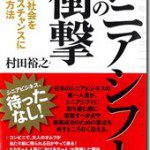2012年12月10日号シルバー産業新聞連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第69回
いま、日本中で「シニアシフト」が加速している。「シニアシフト」には2種類ある。1つは、「人口動態のシニアシフト」。これは、人口の年齢構成が若者中心から高齢者中心へシフトすることだ。
1950年の日本の人口構成は、年齢層が若いほど人口が多い「発展途上型」の形をしていた。所得の低い経済発展途上段階では、このような人口構成がよく見られる。ちなみに、インドやマレーシアの2010年の人口構成は、これによく似ている。2010年現在でも人口増加と経済成長が続いているからだ。
これに対して2010年の日本の人口構成は、人口の山が60~65歳の高齢者層に移動し、年齢が若いほど人数が少ない年齢構成となっている。全体として生産年齢人口(16~64歳までの人口)よりも、65歳以上の高齢者人口が増加する傾向にある。
日本の人口動態は、時間の経過とともに、当初若年層が人口の中心だったのが、徐々に高齢者層中心にシフトしてきたのである。このようなシフトは、日本以外の多くの経済先進国でも見られる。
一方、もう1つのシニアシフトは、「企業活動のシニアシフト」。これは、企業がターゲット顧客の年齢構成を若者中心から高齢者中心へシフトすることだ。
ターゲット顧客を高齢者中心にシフトするには、市場調査、商品開発、商品販売、営業、マーケティング、店舗運営などの事業戦略を大きく変更し、戦略遂行のための組織体制も大きく変更する必要がある。2012年に目立つのは、実はこの「企業活動のシニアシフト」だ。
 私が知る限り、いま、この「企業活動のシニアシフト」が最も先鋭化している国は、日本である。これは裏を返せば、これまで「人口動態のシニアシフト」が、時間の経過とともに粛々と進行していたにもかかわらず、「企業活動のシニアシフト」は、一部の企業と業種を除いて取り組みが遅れ気味だったからだ。それが、ようやく本気モードになってきたのだ。
私が知る限り、いま、この「企業活動のシニアシフト」が最も先鋭化している国は、日本である。これは裏を返せば、これまで「人口動態のシニアシフト」が、時間の経過とともに粛々と進行していたにもかかわらず、「企業活動のシニアシフト」は、一部の企業と業種を除いて取り組みが遅れ気味だったからだ。それが、ようやく本気モードになってきたのだ。
2007年と明らかに異なるシニアシフトの特徴
なぜ、いま、さまざまな産業で「企業活動のシニアシフト」が起きているのか。実は、2012年は、団塊世代の最年長者である1947年生まれが65歳、つまり定年に達する年なのだ。
 人数の多い団塊世代が徐々に定年を迎え、今度こそ大量の離職者を対象とした新たな事業機会が生まれるとの期待感から一種のブームになっている。このことが理由の1つであるのは確かだ。しかし、これだけがいま起こっている産業界全体のシニアシフトの大きな流れの理由ではない。
人数の多い団塊世代が徐々に定年を迎え、今度こそ大量の離職者を対象とした新たな事業機会が生まれるとの期待感から一種のブームになっている。このことが理由の1つであるのは確かだ。しかし、これだけがいま起こっている産業界全体のシニアシフトの大きな流れの理由ではない。
実は、5年前の2007年にも「2007年問題」と呼ばれ、似たようなブームが起きた。人数の多い団塊世代の最年長者が2007年に60歳になり、一斉に退職すると見なされ、急激な労働力不足と後継者不足による技術継承の問題が叫ばれた。
同時に、新しい巨大な退職者市場の出現も期待され、メディアや産業界は大騒ぎした。しかし、結局、そうした急激な変化は起きなかった。
その理由は、拙著『団塊・シニアビジネス「7つの発想転換」』(ダイヤモンド社)、『リタイア・モラトリアム』(日本経済新聞出版社)で指摘したように、1つは団塊世代の半分以上は女性であり、60歳になる以前に多くの人がすでに退職していたこと。
もう1つは男性も多くの場合、定年になっても再雇用され、給料が下がりながらも定年前と同じ会社で働き続けたことだ。
こうして「2007年問題」は一過性のブームに終わり、翌2008年になると鳴りを潜め、その年の後半にやってきたリーマンショックで雲散霧消した。
ところが、今回の動きは5年前の一過性のブームとは大きく様相が異なっている。どう異なっているのかというと、①企業におけるシニアビジネスへの取り組みが本気になってきたこと、②取り組む企業の業界が多岐にわたっていることが挙げられる。
5年前も、マスコミを中心に団塊世代向けビジネスへの関心が高まったが、実際に本気で取り組む企業の数は限定的で、様子見のところが多かった。
一方、今回の動きは単なる団塊世代退職市場ブームという次元ではない。今後、長期にわたって継続的に起こる社会構造の変化への対応としての取り組みが目立つ。
この意味において、2012年は「シニアシフト元年」とも呼ぶべき区切りの年と言えよう。私は、多くの企業経営者・実務担当者とのビジネス現場でのやりとりを通じて、このことを肌身で実感している。
「シニアシフトの衝撃」の詳しい目次・書評はこちら